整理収納の『5つの鉄則』を使い、お部屋を使いやすくしよう。

「あ〜!もう!片付けられない!!」
そんなふうにして、お部屋の片付けができずに、何もかも嫌になっているあなたへこの記事を贈ります。
こんにちは、整理収納アドバイザーのみくとです。

よろしくお願いします!
この記事では、お部屋の片付けに必要な、整理の実践的な知識についてお話しします。
整理収納アドバイザーの勉強でも習うのですが、それを噛み砕いて、僕なりに分かりやすくしました。
色々な本や雑誌を読んだり、動画を見て片付けのやり方を学んでも、実際に片付けをするには、技術が必要です。
そこで今回は、整理に関する基本の技術『5つの鉄則』をお伝えしたいと思います。
この『5つの鉄則』を学ぶことで、使いやすく、キレイなお部屋を簡単に目指すことができます。
そして、応用することで、自分らしい豊かなお部屋にすることだって可能なのです。
- 実践的な片付けの仕方。
- 整理収納の技術
- 使いやすいお部屋作りの仕方。
整理の『5つの鉄則』
1・適正量の決定
2・動線・動作上の収納
3・使用頻度別の収納
4・グルーピング
5・モノの住所を決める
この5つを実践することで、片付けをより上手に行うことができます。
そして、使いやすいお家を実現することもできるのです。
適正量の決定

適正量の決定は、自分のライフスタイルにあったモノの数ということです。
例えば、週5日がお仕事で、休みの日が土・日の会社員の方がいるとしましょう。
例
週5日の仕事。
週2日の休み。
奥さんが、毎日洗濯機を回してくれる。
仕事はほとんどスーツ。
休日は、土・日のどちらか出かける。
↓↓↓こんな人は↓↓↓
スーツは3着。(着まわしや、長持ちさせるため)
ワイシャツは4着。(連日の雨で乾かないときのため、予備も含めて)
お出かけ用のTシャツは3着。
ズボンは2着。
部屋着が2着。
もちろんこれは例に過ぎません。
あなたの生活サイクルは、あなたにしか分かりませんし、それに合わせた適正量も変わってきます。
片付けを通して、不要なモノを手放した先に、自ずと適正量が見えてきます。
あなたが生活している中で、多様なモノが溢れかえっていても、実は本当に使っているモノは数限りです。
不要なモノを手放すことで、自然と使っているモノだけが残り、それがあなたが普段使っている数ともなるのです。
自分の適正量が分かれば、それ以上の数になった時、モノを持ち過ぎていることが分かります。
いわば適正量とは、所有数の基準ということです。
つまり、不要なモノを手放した後に、残ったモノの数があなたの適正量だということ。
適正量を基準に、モノの持ち過ぎや不足が分かりやすくなる。

ぜひ適正量を考えてみよう!
動線・動作上の収納

同線・動作とは、日常の動きのことです。
動線は、お家の間取りに合わせて、その動きは異なってきます。
例えば〈二階建てのお家〉と、〈平家のお家〉、どちらにしてもその動きは異なります。
洗濯物を干す場合、二階建てのお家は大体二階のベランダに干すため、階段を上がります。
そういった家事の“動線”や、そのお家に住む人の身長や家族構成によって“動作”も変わります。

身長の高い人には、高めにモノを配置。
小さい人には、低めの位置にモノを収納します。
そして、一番モノを置きやすくしまいやすいのは、中腰くらいの高さです。

しまいやすいけど、そこに集中してモノを置きがちになり、散らかりやすくもあるから気をつけて!
これらを踏まえ、モノの置き場所を考えていくという方法です。
家事・育児の動線や、人の動作に合わせて考える片付けの方法。

ちょっと難易度高め!
使用頻度別の収納

| 使用頻度 | 例 |
|---|---|
| 毎日 | スマホ・お財布 |
| 2、3日に一回 | エコバック・掃除機 |
| 週一 | スポーツウェア・勉強道具 |
| 月一 | 家計簿・キャンプ用品 |
| 年に一度 | クリスマス(行事)用品・喪服 |
使用頻度って聞いたことはありますか?
つまりは一定の期間内で、モノを使っている回数(頻度)のことです。
毎日使うスマホやカバン、スーツなどは出しやすい手前の方に収納し、週に一回程度しか使わないモノは奥にしまったりするのが、この方法です。
| 使用頻度 | 例 |
|---|---|
| 毎日 | スマホ・パソコン |
| 2、3日に一回 | 本・ハンカチ |
| 週一 | お財布・カバン |
| 月一 | 銀行カード・家計簿 |
| 年に一度 | 病院の診察券 |

あなたも考えてみよう!
僕の場合、お財布とカバンは週一のお買い物に使うので、割と出しやすいところにしまってあります。
月一の家計簿などは、奥のスペースに収納してあり、オフシーズンのモノは押し入れの奥にしまい込んでいます。
僕の例以外にも、月に一度のモノは他にもあり、例えば喪服やドレスなどといった、いつ起こるか分からないモノも含まれます。
こういったものは、すぐに必要となる場合が少ないので、奥の奥にしまい込んでしまって大丈夫です。
反対に、毎日使うモノは、手前に収納しておきます。

俺は毎日使うPCとスマホに関しては、しまう場所を設けてない。
スマホやパソコン、お仕事をしている人であれば定期券や書類などもそうでしょう。
使う頻度別に、取り出しやすさを変えていこう。

これが使用頻度別の収納方法です!
グルーピング

グルーピングは、複数のモノで、同時に仕事をするモノたちをひとまとめに収納する方法です。
例えば、メイク道具は、鏡・アイロン・くし・メイク用品など、お化粧をする際に、複数のモノを必要とします。
それを、ひとまとめにしておくというのが、この“グルーピング”という技術です。
一つのことで、複数の場所から道具を持ってきたり、違う場所にわざわざしまうのは面倒。
この面倒臭さが、結局お部屋の散らかる原因となるため、あらかじめひとまとめにしとおく。

グルーピングは、めんどくさがりの人ほど非常に有効な手段。
モノに住所を与える

モノに住所を与えることは、片付けのゴールとも言える技術です。
自分のライフスタイルに合った収納や置き場所を決めたら、そこをそのモノの専用の場所と決めてしまうという方法です。
そうすることで、モノを探すという無駄な時間を回避でき、モノを戻すことが簡単になり、片付けのルーティン化もできやすくなります。
ラベリングなどを使って、片付け後に、モノに住所を与えてみましょう。
ラベリングなどを施し、モノに専用席を作ることで、片付けが簡単になる。
そして、そこの専用席にモノを戻すことが習慣になる。

習慣は最強の味方。
暮らしに合わせて見直す

さて、片付けの技術を習い、それを実践して「はい、終わり」ではありません。
この技術を使って、定期的に見直す必要があります。

使いづらいな。と思った時は見直しどき。
定位置や、使用頻度、同線動作上のモノの配置を、より使いやすく変えていきましょう。
そうすることで、日夜変化する暮らしの中でも、上手に小片付けができます。
そして、常に使いやすくストレスのない空間を維持できます。
まとめ

1・適正量の決定
2・動線・動作上の収納
3・使用頻度別の収納
4・グルーピング
5・モノの住所を決める
この5つの片付けの技術を使い、あなたのお部屋をもっと暮らしやすく、使いやすい空間にしてみましょう。
どれも豊かな暮らしに欠かせない要素です。
特に、適正量の決定は、個人的には皆やっておいた方が良いと考えています。
自分の必要最低限の数を知ることは、ミニマルに暮らすためにも、お部屋をリバウンドさせないためにも欠かせません。
その必要最低限の数が基準となり、モノが増えるのを防いでくれます。
是非、モノを手放すことから始めて、今回の技術を使い、片付けを進めてみてください。
ブログ村に参加しています。フォローよろしくお願いします!
にほんブログ村








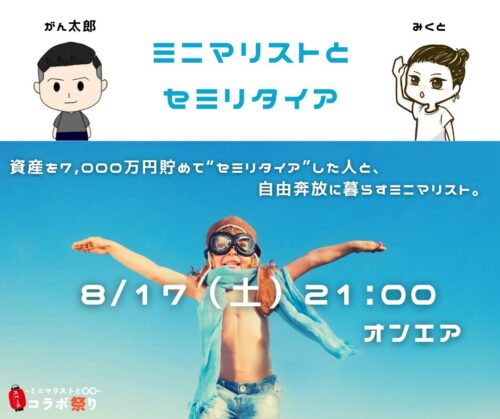

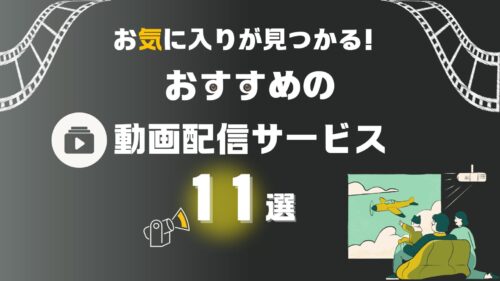
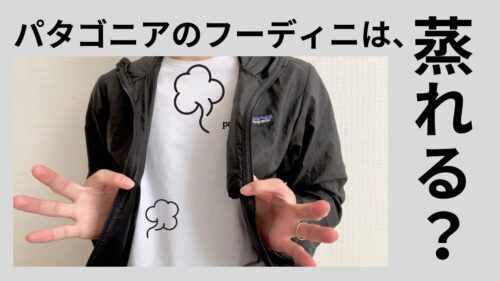

コメント